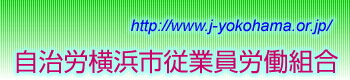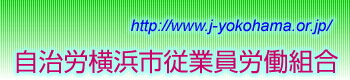1、地公三単産統合と名称問題とは?
(1)自治労は、03年に決定した「21世紀宣言(組織戦略構想)」で、公共サービスを担う全ての労働者・労働組合の結集を訴え、公務・民間・公益セクターの労働組合が対等の立場で参加する新しい質の産別組織の形成を組織戦略としてきました。そしてこの間「全競労」「全国一般」との組織統合を行い、今回地方公務員労組である「都市交」「全水道」「自治労」の組織統合を決定してきました。
(2)具体的には「自治労(約91万人)=全日本自治団体労働組合」、「都市交(約3万人)=日本都市交通労働組合」と「全水道(約3万人)=全日本水道労働組合」との三産別の統合に向けて、07年にそれぞれの大会で理念や枠組みについて確認を行い、地域公共サービス労働組合連合会を設置しました。そして3年後の完全統一をめざして、具体的な課題(綱領・運動や組織のあり方・財政など)の整理を行うため、統一組織委員会で現在協議が行われています。
(3)この統合にあたり、都市交と全水道は組織を解散して新たな産別組織へ合流する、自治労は新たな組織へ移行することで合意しています。従って、新たな産別は三組織でない新たな名称とすることが求められています。
2、自治労横浜の基本的な考え方について
(1)私たち自治労横浜の歴史は、一言で言えば、「全労連(共産党系)」との組織闘争の歴史であったと言えます。1974年に統一労組懇(共産党系)が結成され、当時の従前市従内では、本部役員選挙のたびに自治労系との組織闘争が行われ、また運動方針や具体的な取り組みの分野でも、路線論争が行われ、支部・職場段階から日常的な攻防が繰り広げられました。そして、1990年、自治労が官民統一の連合へ参加するに際し、従前市従内で共産党指導の新たなナショナルセンター「全労連」への参加を強行し、組織を分裂させる策動がありました。その中で、私たちは自治労の旗を守るため、自治労横浜市従業員労働組合(自治労横浜)の再建を行いました。
(2)そして再建時には、正当にそれまでの自治労を上部団体とする「横浜市従業員労働組合」を継承する証として、「自治労」を単組名称に冠することにしました。また、90年の組織闘争を共に闘った全国の単組も同様に、「自治労」を冠としています。つまり「自治労」と言う名称が、全労連との運動の明確な違いとして、象徴になっています。今回の産別統合にあたって、新産別名称が「自治労」であり続けてほしいとの思いは、自治労横浜としては、極めて強いものがあります。しかし、このことが、「都市交」「全水道」との統合の妨げになるとすれば、具体的な新産別名称の議論の中で、新しい産別にふさわしい名称について、判断せざるを得ないと考えます。
(3)その上で、以下の2点について、単組の意見としたいと思います。
単組名称については、強制するものではないことが確認されています。自治労横浜としては、全労連横浜市従との組織闘争が続く間は、「自治労横浜」を単組名称とします。
市労連運動(全労連を含めた運営)について、産別統合後は当然ですが、「横浜交通」「横浜水道」とは同じ方針の下で取り組み、当局交渉や地域労働運動への対応が展開されます。従って全労連との関係だけの市労連組織は見直しが必要です。また、大都市労連についても、自治労名古屋や自治労広島は、市労連から排除されており、自治労組織は参加できていません。組織的にも問題があります。統合後の産別として、「労連組織のあり方」についての検討が必要となっています。
3、今後の方向について
(1)自治労は5月末に第136回中央委員会を開催し、本年8月末の大会に向けて「地公三単産の組織討議と名称問題への対応について(討議案)」が確認されました。
(2)自治労横浜は、8月の大会に向けて、上記の考え方を基本に単組内討議を進めたいと考えています。要約すれば、
(1)統合後の新産別名称は、自治労への拘りはありつつも、新名称の議論の中で判断する。
(2)単組名称の自治労横浜は変更しない。
(3)統合後の労連組織のあり方について、意思統一を行っていく。
以上の3点を自治労横浜の考え方として、今後組合員の皆さんと意見交換を行いながら、大会に臨んでいくこととしたいと考えています。 |