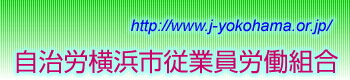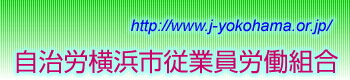中田市長の行状がこの間「週刊現代」に連載され、世間の耳目を集めている。
一方時期を同じくして横浜市で職員行動基準作成が進められている。
また、職員満足度調査では「全ての事故やミスを公表する横浜市のコンプライアンスの姿勢をどう思いますか」との質問が発せられている。
大局に目を塞ぎ、些細なミスに血道をあげ、職員のストレスと疲弊を生む
くどいようだが横浜市のコンプライアンス(運動)は、横浜市役所の市長以下最高幹部が前港北区長石坂氏の要請に応えて、市の行政組織を選挙運動に動員した組織「犯罪」の元を断つ、との理由から考案されたものである。しかしそれは元を断つというよりはすり替えといったほうが良い。何がすり替えかといえば、大きな問題に目が行かないよう、些細な問題を洗いざらい穿り出し衆目の目をそちらに向けるという、よくある手法である。
誤送付、誤発行に限らず、ありとあらゆる些細なミス、当事者との間で対応すればよい問題をあえて新聞発表する。ある職場で、受け付けた書類が一時的に見当たらなかったとき、係長が飛んで来て、一緒に書類を探すどころかいきなり「見つからなかったら新聞発表だ」と脅しつけたという。倒錯しているというほかない。何で管理職がこんなに意図通り動いてしまうのか。それこそが本当のコンプライアンスの核心ではないのか。
品性が問われ、行動に疑念がもたれる中田市長の全てをチェックし公表せよ
11月8日のコンプライアンス情報(コンプライアンス推進室発行)によると、11月4日の神奈川新聞の記事にクレームをつけている。何にクレームをつけたかといえば、全てのミスの公表で「職場にプレッシャーを与えている」と報じられたことに、職場の反発を恐れて、わざわざ「横浜市自らにプレッシャーをかけている」と弁明している。全く度し難い。どんなに職場個人にプレッシャーをかけ、ストレスと疲弊を生んでいるのか。末端に責任を負わせることが管理職の仕事であるかのような錯誤と「木を見て森を見ない」退廃を生み出しているのだ。それよりまずは、著しく品性が問われ、疑念がもたれている中田市長の全ての行動を公表したらどうか。 |