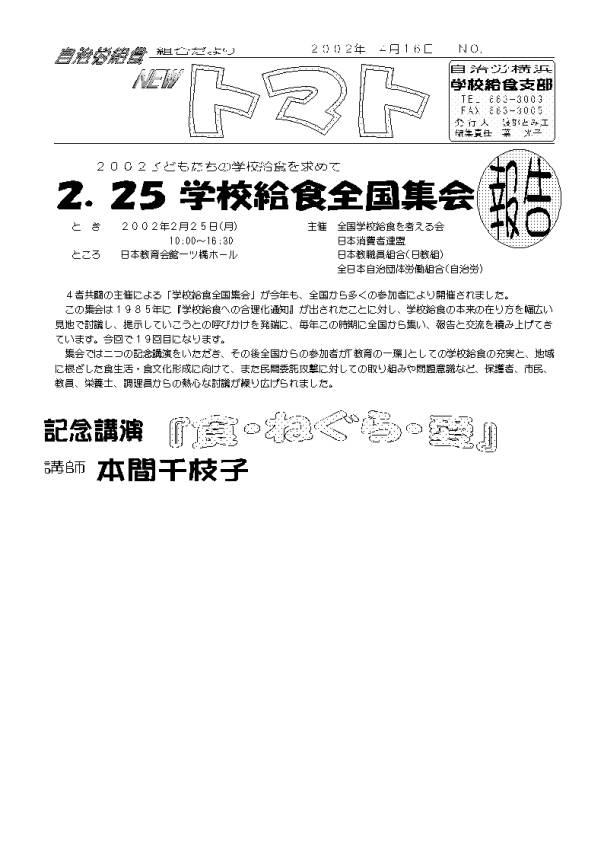
1933年東京生まれ。随筆家。
三鷹市教育委員長、三鷹の森ジブリ美術館理事。
社会史や文学作品にも視野を拡げながら、生活文化を中心に捉えた教育問題、食卓論、人間関係のあり方を探求する。
執筆作品多数。
|
子どもは家族の中の子どもとして生まれ、やがて成人するのだが、ヒトの子が人間に育つのは食卓である。 食卓は人が食事をする時に食べ物、栄養を並べる台というだけでない大きな役割を果たしてきた。空腹を満たし、命を養い、集う人びとの心をくつろがせ、幸せにして悲しみを和らげ、人間が人間であることのつつしみや礼節を教えることに役立ってきた。 家族とはそもそも食の分配をめぐって構成されたものだと、ある文化人類学者は指摘するが、子どもの心身を養い、社会に送り出すために必要な、生きて行く“すべ”を教え、人間としてのマナーを躾る教育の場として、食卓に代わる場は他に何かあっただろうか。 日本では人が生きて行くために不可欠なものを三大要素「衣・食・住」と言い慣わしている。実は西欧にもこの三大要素という言葉は存在する。しかし内容は微妙に異なっている。西欧のそれは「食・ねぐら・愛」である。 さて、日本の三大要素に含まれていない「愛」、現代の日本で、あらためてとり上げて考える必要があるのではないか。 家庭で、学校で、そして地域社会という与えられた環境の中で子どもはどのように食べ、育ってきたのか。 現代だけでなく歴史や物語にもふれながら、これからの学校給食を皆さんと共に考えて行 きたい。 |
【講演内容・要旨】
ヒートアイランド現象などの状況がある。現代の都市は人間にやさしい都市といえるか。8年前に教育委員になり昨年から長になった。生命を養うものとしての食の話をしている。
人間がどんなくらしをしてきたか、食べることに精一杯の時代、そして今日、そうしたことを具体的なことで子どもたちと共有できないか、食材をひとつの切り口として、食物の存在と社会、知識の教えこみでない形。食材について教える、しかし覚えていることは物語としての展開の中にある。
社会はその主食に影響される。米が主食としてあると、社会も米に支配される。米の持つ社会的位置、生産、消費の状況。言葉にも新米、票田、等々、米に関係する言葉が数多くある。世界の様々な米について教える、教室で子どもたちは歓声をあげた。こんなにも多くの珍しい米がと。そして世界の米作りなどを学ぶ。
食卓は子どもの成長にとって大切です。そこに毒が入ってきた。水俣病や様々な食品汚染など。
子どもたちが調理に取り組んでみると様々な発想が広がる。魚、海、くじらと。学校給食が食教育として、食材や食事をつうじた食の物語として展開すると豊かなものになる。
給食の内容は充実し、より良いシステムとして作り上げてきたが、いま、子どもたちの救済が必要となっている。昔、家で語られたことがなくなってきた。コンビニ、レンヂ、出来あい、の食。そこで学校給食で補うことを求められてるが、大変重たい。子は学校給食だけで育つものではないから。
誰が作って、どういう調理をし、何を聞いて、そして座って食べるのか、食卓の意味は単なる台ではない。本来は家庭の食卓にある、そうしたものが無くなって、それは学校で担うものなのか考える。社会の問題であり、学校の責任かと。
食卓がいかに大事か、人類は食を持ち帰り、分かち合う。それらの労働をいとわない。人が人間に育つ場、それが食卓。くつろぎ、みたされた気持ち、物理的に空腹を満たすだけでない。ミルクと食べ物だけで人間は育つのか。肉体的、精神的発達がなくてはならない。
西欧の三つの基本的要素「食・ねぐら・愛」である。
愛は食卓の形と分かちがたく結びついている。ねぐらの中の女が培ってきた。男が外から食を持ってきて、女が作ってきた。子どもの傍らに四六時中いる女の負担。男は日の出から日の入りだが、女の一日は終わりがない。女は家族の生命を預かる。母性愛でもある。
外食産業が増えたり、出来合いの惣菜を買ってきて食べる。女性の愛の形が変わると食べ方が変わる。これは女の自立や社会進出などの変化もある。家庭のワークシェアリングが変化してきている。
子どもは食卓で育つ。そういうことから学校における食卓の意義の大きさが目立ってきた。子どもたちはどこで学習するのか。家庭でも、給食でもやる。学校給食がかっての家庭の食卓の果たす役割を求められている。
そして食を通じて、食べ物の向こうに拡がる世界を学ぶことが出来る、それが大切。
食材の安全に関し、保護者からの要望、声、ひとつもない。野菜の畑など見て廻るということもない。安心と信頼をしているからと思うが、保護者も努力を惜しんではならない。
愛を深めて、子どもが社会を生きるルールを教えていこう。それらを家族との食卓の中で学んだ。先生だけが教えるのではない。
これから育っていく子どもたちの危機を乗り切るために、食を切り口として話をした。
(報告は60分の講演の要旨です。文責 佐竹)
|
※ 本間千枝子さんの著書「毒を盛るか愛を盛るか」を購入しています。 読んでみたい方は本部佐竹現業部長まで連絡して下さい。 メール便で送ります。読み終わったら返却。 |